
the most unuseful
website in the world
|
 |
| ジッチャンの名にかけて。 |
2-1 「気になるお年頃」
キト (  エクアドル)
|
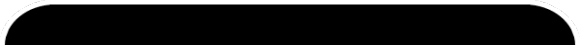 |
南米に入ると、急に町が大きくなった。
キトはエクアドルの首都。
だから大きいのは当然だが、今まで見た中米の首都たちと比べると、格段にデカくて近代的だ。
南米は中米の数倍ハードだぞっと構えていたが、実際はむしろ逆だった。
考えてみたら面積も人口もケタ違いに大きいのだ。
こっちの方がはるかに発展していて、旅しやすそうだった。
町が大きくなると、物乞いの数も増えた。
人間の数が増えたので比率はそう変わらんだろうが、やたらあちこちで目に付く気がした。
この頃のエクアドルは激安国で、1日3食と宿代足しても、300円前後で生きていけた。
だが、それは外貨を持っているわしらにとっては、で、
インフレしまくっている中を地元の人たちが生きていくのは、たいへんだったのだ。
とくに物乞いが多いのが、教会だ。
発展途上国において宗教施設とホームレスはセットみたいになっている感があり、
世界遺産・キトのカテドラルの石段にも、
ナンパ待ちのギャルかというくらい、物乞いがパンツを丸出しにして群れていた。
その中に、ある家族連れがいた。
教会の扉の前に1人のオバちゃんが陣取っていて、周りには3人の子供たち。
中学生くらいの女の子と小学校低学年くらいの男の子、そして、4、5歳の男の子。
先住民の子孫、民族衣装を着たインディヘナの家族だ。
彼らは朝見ても夜見ても、いつも同じ場所で、いつも同じポーズで座っていた。
物乞いは 「ダンナ〜 お恵みくだせえ〜。」 みたいに攻めの姿勢でくる奴が多いが、
その家族は一言も喋らず、ただ右手を出して、石像のように微動だにしない。
死んでいるのではないかと思うくらい、根が生えたように動かない。
何曜日の何時に見ても同じなので、あまた居る物乞いの中でも、際立って気になる存在だった。
飲むことも、食べることもしない、植物のような一団。
彼らはもう、そこから動くことなく朽ち果てていくのだろう。
キトの住民だったら待ち合わせの目印に使いたいくらい、もはや名所の風格が漂っていた。
ところが、深夜まで新市街で飲んでいたある日。
帰りにそこを通りかかると、教会の前に彼らの姿は無かった。
他の物乞いはその場で寝泊りしている者が多かったが、あの家族連れがどこにも居ない。
しかし、翌朝になると、また何事もなかったようにいつもの場所に陣取っていたのだ。

彼らにも家があるのか?
というか、動けるんかい。
それもそうだ。 彼らに気づいてから、もう1週間になる。
いくらなんでも飲まず食わずなら、ずっと生きてるはずがない。
一体どこへ帰ってるんだろう?
メシはいつ食ってるんだろう?
そんなどうでもいいことに、不思議なほど興味がわいた。
好きな食べ物はなんだろう? 趣味は? 愛読書は?
私生活にまでこれほどの興味を抱かせる相手は、芸能人にもいなかった気がする。
ある夕方。
わしは教会の石段に腰掛けて、広場を見るふりをしながら家族の様子を伺った。
相変わらず4人とも固まっている。
家族なのに、会話もないようだ。
夕日は石造りの町並みの彼方に沈もうとしていたが、彼らが動き出す気配はなかった。
だが、地震なんかと同じで、こういうものに前触れなどないのだ。
母親がスッと、音も無く立ち上がった。
山が・・・動いた。
それだけで感動的だった。
ゆっくりとした、それでいてムダの無い、流れるような動作でパタパタとスカートを整える。
空腹だから、エネルギーを消費しない道を突き詰めた結果だろうか。
歩き出すまでの一連の動きには、相撲の土俵入りのような様式美が感じられた。
続いて3人の子供もそれに追従する。
家族は広場を出て、旧市街の更に下町に向かって歩いて行った。
ここまで来ると自然な流れで、後をつけてみたい衝動にかられた。
日本で女の人にやったら大変なことになるが、これはストーカーではない。
あくまでも学術的な研究なのだ。
ホームレスに、ホームはあるのか・・・?
彼らの歩みは遅い。
バレないように遠巻きに、
しかも見失わない距離を保って追跡するのは、なかなか大変な作業だった。
インディヘナ色の強いエクアドルでも、東洋人の存在はやたら目立つ。
尾行にもそれなりの苦労があるのだと知り、本業の人リスペクトだ。
そろそろ暗くなってくるので、町の危険度もアップするはずだ。
キト旧市街はガイドブックでも 「夜は出歩かないこと」 と書かれている。
ヘタすると自分がつけられて襲われる可能性の方が高い。
だが、ここまで来て、手ぶらで帰るわけにはいかない。
帰り道を見失わない程度に、行けるところまで行こうと追跡を続ける。
もう20分は歩いたか、世界遺産なのに、外国人など1人も見かけないエリアまで来てしまっている。
と、突如母親が足を止めた。
しまった、バレたか・・・?
この時間は誰も居ないが、日中は市場だったと思われる場所の片隅。
そこにはゴミ捨て場というか、ゴミの山があった。
日本のゴミ捨て場みたいに、行儀よくビニール袋が積まれた感じではない。
むき出しのゴミが分別もされずに山になっていて、ハエが群がっている。
わしの存在ではなく、ゴミが気になったようだ。
母親はおもむろにゴミの山をあさり始めた。
小さな子供が二人、それに続く。
分身のように同じ動きで、食べられそうなものを物色していく。
しかし。
しかし、だった。
いちばん年長の女の子、
12〜13歳くらいの少女だけは、2mほど距離をおいて、それを見守るだけだった。
決して手を出そうとはせず、
時々家族に背を向けるようにして、
「私はこの人たちとは関係ありません」 というようなそぶりさえ見せている。
辺りには人通りもほとんど無い。
見ているのは、坂の上の物カゲからピーピングしている東洋人ぐらいなのに・・・。
思春期に芽生えた小さなプライドが、彼女と家族の間に距離を取らせていた。
そこに、人生の縮図があった。
小さい時は、親のやることにただ従う。
そうやって子供は、いろいろなことを吸収していく。
しかし、ある程度成長すると、今度は自我や道徳に目覚め、
善悪や貴賤の判断といったものを、自分の中で消化するようになるのだ。
こんなことは日常的に行っているのだろうが、
彼女はゴミあさりを 「恥ずかしいこと」 と認識して、拒否した。
そして成熟した大人・母親は、生きるためには誇りより優先すべきものがあると知る。
そこには生命としての覚悟と、また別のカタチでの尊厳が感じられるのだ。
ゴミはあさらなくても、同じことは日本人にも当てはまるな、と思った。
幼稚園児や小学生は親の言うことをきくが、中学生はそうはいかない。
生活のために、甘んじて誇りを捨てる大人もいる・・・。
おそらくは学校も行っていないようなインディヘナと、我々は全く同じなのだ。
人は、どこに居ても人だった。
なぜだか心に沁みる、感動的な時間だった。
燃え上がる炎のような紅蓮の夕日を背にして、
4つのシルエットは道の両側、3と1にクッキリと分かれていた。
この光景が宇宙の真理を語りかけてくるようで、息を呑んだ。
わしはそれを、この世でいちばん美しいものでも見るような目で、ずっと見守っていた。
ゴミ捨て場でストーカーがホームレスに感動する。
俯瞰してみると、それはシュールなひとコマができあがっていた。
|
■ 次の事件簿を読む >>
|
 |
<< このページのTOPへ
|
|
| 1999-2009 (C) GamecenterKomine all rights reserved. |



